特許:5416288号
特許:2630903号
商標:4536804号
回転寿司企業の中でもトップクラスの人気を誇る「くら寿司」。
知的財産戦略で競争優位性を確保
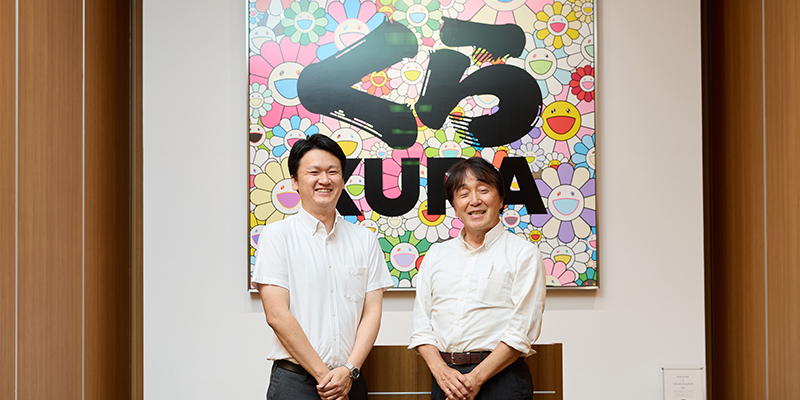
ほとんどの回転寿司チェーンがコロナ禍以降お寿司を回さない中、くら寿司は自社独自開発品である「抗菌寿司カバー」(「飲食物搬送用収容体」特許第5416288号)を採用することでお寿司を回す伝統のスタイルを守り続けています。
また、食べ終えた皿を回収する「水回収システム」(「飲食店における皿の回収装置」特許第2630903号)や、5皿ごとにゲームに1回挑戦できるシステム「ビッくらポン!®」(商標登録第4536804号)など、効率性とエンターテインメント性を兼ね備えたサービスを提供しています。
今回は大阪府貝塚市にある社屋で、自社で開発したシステムやその開発経緯、知的財産への取り組みや今後の展開などについて伺いました。
~抗菌寿司カバーや水回収システム、店舗の内装まで幅広い知的財産の取得~
- 取材担当者
- 最近はお寿司を回さない回転寿司チェーンがほとんどです。レーンを回ってきた好みのお寿司を取るのではなく、注文したお寿司がレーンから直接運ばれてくるシステムですね。

- くら寿司
- 各社が、いわゆる回らないお寿司に舵を切ったのは、コロナ禍や相次いだ迷惑動画の影響が大きいです。しかし弊社は2011(平成23)年に、食品衛生を保つための寿司カバー「鮮度くん」を開発しました。以来改良を重ね、今も「抗菌寿司カバー鮮度くん」として大活躍しています。この製品のおかげで、弊社では今も、レーンにお寿司を回す回転寿司の本来のスタイルを守り続けています。
- 取材担当者
- 抗菌寿司カバーは、2013(平成25)年に「飲食物搬送用収納体」(特許第5416288号)という名称で特許を取得されています。透明で中身がよく見えますし、下部にあるボタンを押すだけでカバーが開き、中のお寿司を皿ごと簡単、スムーズに取り出せます。
- くら寿司
- きれいに洗浄できる設計ですので、何度でも繰り返し使えます。
- 取材担当者
- 食べ終えた皿を水路につながる投入口に入れる水回収システムも、「飲食店における皿の回収装置」(特許第2630903号)という名称で、1997(平成9)年に特許を取られています。そもそも食べ終えた皿をテーブル上に重ねず、回収することにしたのは効率性を重視されたのですか?何か他にも理由があったのでしょうか。

- くら寿司
- 多分男性は、自分の食べた皿を積み上げて満足なさる方が多いでしょう(笑)。女性は逆です。積み上がっていく皿の数が恥ずかしくて、食べるのを我慢する方が多かったのです。そこで、私たちは人目を気にせず好きなだけ召し上がってご満足いただきたいとの思いが、水回収システムを開発するきっかけとなったのです。

- 取材担当者
- 水回収システムの開発には、かなりご苦労されたと伺いました。
- くら寿司
- 苦労したことの一つとして、投入口から水が流れる下のレーンまでの傾斜角度があります。角度がきついと当たった皿で機械にダメージが生じますし、緩いと内部で皿が詰まります。ちょうどいいスピードで落とし、さらに洗い場までスムーズに皿を流す仕組みづくりに苦労しました。
- 取材担当者
- テーブルから皿がなくなれば、広く使えますし清潔ですね。
それから、御社の特徴は何といっても「ビッくらポン!®」だと思います。投入口に5枚、お皿を入れるとゲームが始まりますよね。特に子どもたちに人気です。
- くら寿司
- 「ビッくらポン!®」は、社長の発案なのです。投入口に競って皿を入れて喜ぶ子どもたちを見て、「もっと面白くしよう」と、最初は5皿入れるとルーレットが回り、当たると目の前の人形がダンスするというゲームでした。それが人気を集め、現在はタッチパネル式のゲームになり、特に最近はアニメとコラボレーションしてさらに人気を集めています。
- 取材担当者
- この「ビッくらポン!®」は、2002(平成14)年に、商標登録されていますね(商標登録第4536804号)。また、「ビッくらポン!®」に関する技術についても「皿回収装置」として、2006(平成18)年に特許を取得され(特許第3859962号)、まさにお客様に楽しんででいただきたいという発想が、他社にないアイテムを生み、形になった独自のサービスを特許や商標で守っているわけですね。


- くら寿司
- そうなのです。ちなみに「楽しませたい」、「びっくりさせたい」といえば、弊社では2024(令和6)年11月に、お誕生日などお祝いの日に抗菌寿司カバーに入ったケーキがレーンを流れて来るサプライズ演出「プレゼントシステム」を始めました。順次店舗に導入中で、ファミリー層の来店動機につなげています。特許権(たとえば、「飲食店用移動体および飲食店用搬送システム」特許第7549284号)があるからこそ、自社の強みを存分に打ち出すことができます。
- 取材担当者
- 2020(令和2)年には、日本初の内装意匠「回転寿司店の内装」(意匠登録第1671153号)を取得されています。非常にユニークですが、何か出願するきっかけがあったのでしょうか。
- くら寿司
- お寿司が回るというエンターテインメント性は、私たちが想像する以上にインバウンドのお客様に喜ばれています。そこで弊社はさらに日本文化を楽しく盛り上げていこうと、大手回転寿司チェーン初のジャパンカルチャー発信型店舗として「グローバル旗艦店」第1号店を、東京・浅草にオープンし、このお店の内装を意匠登録しました。このような内装の意匠を特徴とするお店を現在インバウンドが多く集まるエリアを中心に、6店舗を展開しています。浅草店は日本の「祭り」をモチーフに、大阪(道頓堀店)はとにかく派手にカラフルにと、店舗ごとに店内エンターテイメントとなる特徴的なコンテンツを導入し、喜ばれています。
- 取材担当者
- 第1号店の浅草店には、昔懐かしい射的があるんですね。

- くら寿司
- この「ビッくらポン!射的®」(商標登録第6553650号)も商標登録させていただいています。他に飲食用の皿や、中の汁がこぼれないための「椀蓋用止め具」も特許(特許第6078495号等)を取っていますし、湯呑みは意匠登録(意匠登録第1692057号)をしています。そして当然ながら、くら寿司のロゴ(商標登録第6465249号等)も同じく商標登録済みです。
~特許が参入障壁になっていたからこそ、特許の価値に気づけた~
- 取材担当者
- 同業他社に比べても、御社は特許や商標登録数がかなり多いですね。
- くら寿司
- 現在、特許が約60件。商標登録数においては600件ほどあります。

- 取材担当者
- なぜ、御社は知的財産に積極的なのでしょうか?
- くら寿司
- その理由は、弊社の成り立ちにあります。日本で初めて回転寿司の店を出されたのは、東大阪市にあった「元禄寿司」さんです。1958年に、ベルトコンベアシステムで特許を取得されました。1970年の大阪万博の会場近くに店を開いたのを機に、回転寿司は一気に全国へ広まり大人気になったのです。
- 取材担当者
- お寿司が回ってきて、食べたいお寿司を自由に取って食べるというエンターテインメント性がウケたのですね。でも、元禄寿司さんが特許権を持っていたので参入できなかったと伺いました。
- くら寿司
- そうなのです。回転寿司を開業するには、フランチャイズで開店するしかありませんでした。弊社は1977(昭和52)年に「お持ち帰り寿司」で創業し、1978(昭和53)年に元禄寿司さんの特許が切れたのを機に回転寿司として開業しました。1984(昭和59)年のことです。

- 取材担当者
- その頃から、特許などの知的財産権の重要性について認識されておられたのですか。
- くら寿司
- もちろん認識していました。創業者で現社長の田中邦彦は、回転寿司への参入ができなかった理由が特許だったことから、特許は自社の強みや特徴を守るものであり、他社との差別化を図るうえで重要だということを深く理解していました。それは今も変わりません。経営会議で新しいサービスなどが議題にのぼれば、すぐに特許が取れるかを確認し、社外の弁理士さんに協力して貰って権利化を進めています。
- 取材担当者
- 経営会議の場で、特許の話題が出るのですね。
- くら寿司
- もちろんです。すぐに「このサービスは特許が取れるか」という質問が飛びますし、そこで社内の弁理士が「このままでは難しいが、これとこれをこのようにすれば取れるのでは」と発言するなどすることで、スムーズに議論が進みます。そのため、弊社では社内の弁理士がいつも経営会議に同席しています。

- 取材担当者
- 御社の知的財産の管理に関する社内体制はどのようになっていますか。
- くら寿司
- 法務管理部門の中に知的財産部を設けています。専属でいるのは1名ですが、社長をはじめ会社全体が知的財産全般に積極的です。

- 取材担当者
- 御社の経営者層は知的財産への理解が深いですが、知的財産に関する教育を行っておられるのでしょうか。
- くら寿司
- 以前から商標や意匠、特許といった知的財産の話題はよく出ていましたね。社内に弁理士が入社してからは、例えば先日は経営会議メンバーで、特許制度やPCT国際出願制度といった知的財産の研修を開催しました。
- 取材担当者
- 経営層の方が知的財産について勉強しようという、高いモチベーションが素晴らしいと思います。
~特許は、海外展開するうえでの武器となる~
- 取材担当者
- 御社は米国や欧州、中国などの海外展開も積極的です。実際、回転寿司業界でも海外における特許出願数と登録数はトップだと伺いました。ご苦労されたエピソードはありますか?
- くら寿司
- 2009年に米国を皮切りに海外進出を行っています。米国は特許に対する意識が高く、そうした意識の違いはもちろんのこと文化の違いも大きいです。米国では、むき出しの食物をレーンで流すことはできず、必ずカバーをする必要があります。そこは弊社の抗菌寿司カバーで文字通りカバーできましたが、そもそも回転寿司という文化がない国では、「なぜお寿司をレーンに流す必要があるのか」をわかってもらう必要がありました。

- 取材担当者
- まさに、回転寿司という文化のない国に出店されるご苦労ですね。
- くら寿司
- それでも海外のお客様は、お寿司が回ることそのものに非常にエンターテインメント性があると、大変楽しんでくださいます。だからこそライバルも現れます。その中で我々が競争力を保ち、さらに海外に回転寿司を展開していくことを考えると、特許の取得によるメリットは大きいと考えています。
~特許で「楽しさ」と独自の「サービス」、さらに自社の経営を守る~

- 取材担当者
- 今後、御社はどのような展開を考えておられますか。
- くら寿司
- いまや「安心安全」、「おいしい」は当たり前のことです。そのうえで私たちは、お客様に「楽しさ」をご提供します。そのためにこれからも独自サービスを特許で守り、ビジネスの競争力を高めて優位性を確保するために、新たな特許出願や装置の開発を続けていきます。
- 取材担当者
- ありがとうございます。最後に我々弁理士に何か要望があればお聞かせください。

- くら寿司
- 「できない」ではなく、「どうすればできるか」と一緒に考え、提案してくださる社外の弁理士さんは、本当にありがたいと思います。弊社の商品や製品の特性を知っていただいたうえで、「このままでは難しいが、ここをこうすればいけそうだ」と意見をくださるだけでも、ずいぶん助かるからです。
お願いしたいことは、中小企業にとって相談しやすい環境を整えてくださるとうれしいですね。弊社の場合、社長が特許に対する理解が深いのですが、担当者任せという企業も多いでしょう。それは恐らく、経営者が経営において特許が大きな価値を持つことに気づいておられないからだと推察します。特許で自社の技術やアイデアを守ることは、自社の経営を守ることです。すると、よりビジネスがやりやすくなります。そのような知的財産の重要性を企業に伝え、ぜひ企業と特許庁との懸け橋となる役割を弁理士さんが担ってくださることを期待しています。
- 取材担当者
- わかりました。本日は製品と知的財産だけでなく、回転寿司業界に関する貴重なお話もお聞かせいただき、ありがとうございました。

くら寿司株式会社
1977(昭和52)年に大阪府堺市で創業の回転寿司チェーン。北海道から沖縄まで全国規模で展開し、現在も自社で開発した「抗菌寿司カバー鮮度くん」を用いて、回転レーンでお寿司を提供している。寿司カバーをはじめ特許や商標など多数を取得。海外での特許数も多い。特許で自社の製品を守りながら、独自性や存在感を明確に打ち出している。またゲーム「ビッくらポン!®」や、ケーキなどをレーンで提供する「プレゼントシステム」など、日本の食文化の代表であるお寿司を通じて、食の楽しみを提供し続けている。
2025年10月14日掲載




