知的財産を活用しつつ
データやノウハウも
蓄積することで
複合的に製品を守っています。

1919 年の創業から 100 年にわたり、でん粉の新しい価値を創造してきた松谷化学工業。近年はトクホ(特定保健用食品)に欠かすことのできない水溶性食物繊維「難消化性デキストリン」など、でん粉を活用した機能性素材の開発にも力を注いでいます。今回は同社研究所を訪問し、食品分野で高いシェアを実現する製品開発やビジネスモデル、知的財産への取り組みなどについてお聞きしました。
製品だけでなくお客様の用途まで開発する
- 取材担当者
- 御社の主力商品である加工でん粉は、どのようなものに利用されているのですか。
- 松谷化学工業
- 代表的な用途は食品です。でん粉はトウモロコシや馬鈴薯、小麦などから作られますが、原料ごとに特性があり、加工することでさらに様々な機能を付加することができます。最近、おもちのような弾力をもったパンを食べたことはありませんか。あの食感は、加工したでん粉を加えることで生まれるのです。

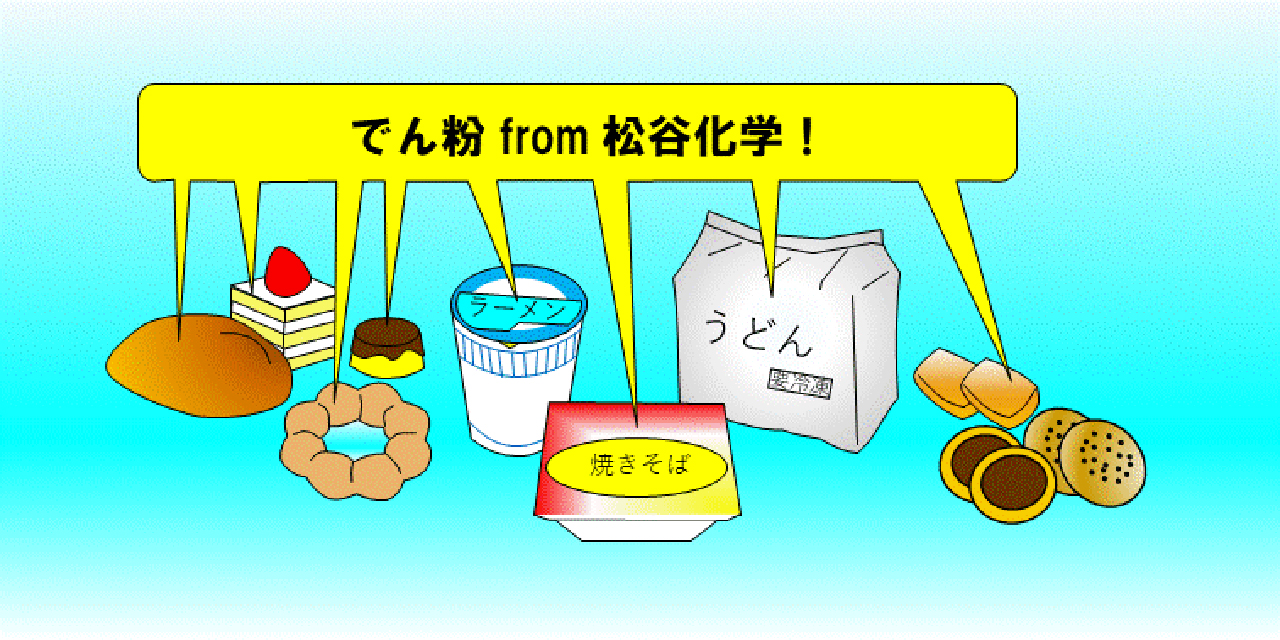
- 取材担当者
- パンではありませんが、実は私、ドーナツ屋さんのもちもちしたドーナツが大好物なんです。
- 松谷化学工業
- パンやドーナツのもちもちした食感は、タピオカでん粉の加工品を加えることで実現できます。また食品の品質の改善にもでん粉は役立ちます。例えば冷凍うどんというのは小麦だけで作ると解凍した時、ボソボソになってしまうのですが、加工でん粉を加えることで、劣化を防ぎ、解凍後も美味しく食べられるようになります。

- 取材担当者
- 御社は加工でん粉で国内シェアナンバーワンだそうですね。お客様に選ばれる理由はどこにあるのでしょうか。
- 松谷化学工業
- 一つはでん粉の加工技術を研究し続け、常に新しい付加価値を持った加工でんぷんを生み出してきたからだと考えています。そしてもう一つは、加工でん粉だけを提案するのではなく、お客様が扱う食品にまで落とし込んでセールスしてきたことが、功を奏したのだと思います。
- 取材担当者
- 顧客がパンのメーカーだとしたら、御社でパンまで焼いて持っていく、ということでしょうか。
- 松谷化学工業
- そうです。加工でん粉だけではお客様の商品にどう役立つかなかなか理解してもらえません。でも加工でん粉を加えたパンを実際に食べてもらえば、効果は一目瞭然です。
- 取材担当者
- お客様の用途まで開発・提案するビジネスモデルが高い成約率につながり、シェアを拡大して行ったのですね。

松谷化学工業- はい。用途開発に力を入れた結果、パン作りや麺作りのスキルも上りました。今では当社のスタッフは、職人さん顔負けのおいしいパンを焼くことができます(笑)
でん粉から生まれた体に優しい食物繊維
- 取材担当者
- 御社は 1980 年代から機能性食品にも力を入れるようになりましたね。
- 松谷化学工業
- 当時、私どもは「社会に貢献する製品を作りたい」という先代会長の意志のもと、健康に資する食材の研究を進めていました。そんな時に出会ったのが食物繊維です。それまで食物繊維は体には不要なもの、と考えられていましたが、研究が進み、有益な作用があることがわかってきていました。
- 取材担当者
- それが今、加工でん粉と並んで御社の主力製品となっている水溶性食物繊維「難消化性デキストリン」開発のきっかけだったのですね。
- 松谷化学工業
- はい。ちょうどその頃、製薬メーカーさんが食物繊維入りの飲料を発売し、ヒットしました。当社で取り扱うでん粉を原料にすれば、自然由来の体にやさしい食物繊維が作れるのではないか、と考えたのが始まりです。
- 取材担当者
- 開発はスムーズに進んだのでしょうか。


- 松谷化学工業
- 試行錯誤の連続でした。例えば製品を無色透明にしたかったのですが、でん粉を加熱すると、どうしても色が付いてしまいます。そこで無色になるよう、精製技術から研究しなければなりませんでした。1988 年、苦労の末、発売に漕ぎつくことができたものの、すぐには売れません。そこで発売後は加工でん粉同様、完成した食物繊維をどのような食品に使うか、という用途開発にも着手しました。
- 取材担当者
- 御社の年表を見ますと 1992 年にトクホ(特定保健用食品)の認定も受けていますね。
- 松谷化学工業
- はい。どういった生理機能があるかを大学との共同研究で調べたり、当時の厚労省や国立栄養研究所とコミュニケーションを取りながら成果を積み上げていき、整腸作用や血糖値の上昇を抑制する作用などで許可を受けることができました。
- 取材担当者
- 用途開発やトクホの許可を取得したことで市場に認知されるようになっていったのですね。「難消化性デキストリン」はどんなものに使われているのでしょうか。

- 松谷化学工業
- 飲料が多いですね。透明で粘度が低いため、飲み物に加えてもほとんど違和感がありません。健康志向のお茶やコーラ、それからビールなどにも利用されています。現在、トクホ商品は市場で1,063 品目あるのですが、そのうち 382 品目に当社の「難消化性デキストリン」が使われています(2019 年 1 月現在)

- 取材担当者
- トクホ全体の 1/3 ですか。この分野でも御社は高いシェアを獲得しているわけですね。「難消化性デキストリン」ではどのような知的財産を取得しているのでしょうか。
- 松谷化学工業
- 物質特許と製造方法の特許、それから食品用途などの特許をいち早く取得しました。ただ、初期の特許は現在ほとんど切れているのです。
- 取材担当者
- これだけ有望な市場で特許が切れているとなると、他社が同様の製品を作り、どんどん参入してくるのではないのですか。

- 松谷化学工業
- 理論的には作れます。しかし現実的には難しいのです。同じようなものを他社が作っても、それは当社の「難消化性デキストリン」と全く同じではありません。ですから他社が同様の製品を作ってもトクホの許可を取得するためにはもう一度、数々の試験を行い、データを採る必要があるのです。
- 取材担当者
- そうなるとコストだけでなく時間もかかりますね。
- 松谷化学工業
- そうです。それともう一つ、当社は「難消化性デキストリン」を使って頂いたお客様が販売する商品について、トクホ表示ができるようにするためのサポート業務も行っています。いわば時間をかけて蓄積したトクホのノウハウを、「難消化性デキストリン」とセットで販売するわけです。ノウハウのない他社さんには簡単に真似のできないことだとおもいます。
- 取材担当者
- 開発初期は特許で製品を守り、その間にデータやトクホのノウハウを蓄積することで、他社が参入できないような障壁を作っていたわけですね。
大学・県との連携で希少糖の製品化に成功
- 取材担当者
- いま、御社は「難消化性デキストリン」に続く新たな機能性食品として「希少糖」にも力を入れておられますね。御社と香川大学さんとの共同開発だと聞いていますが、どういった御縁だったのですか。
- 松谷化学工業
- 希少糖というのは自然界に存在量の少ない単糖の総称です。種類は非常にたくさんあるのですが、どれも量産はできませんでした。ところが香川大学の何森(いずもり)健教授が、大量生産のための酵素と方法を発見したのです。そのニュースを、当時の会長がたまたまテレビで見ておりまして。興味を持った会長は当社の製品開発担当者に、香川大学へ行くよう命じました。
- 取材担当者
- 大学さんとは偶然の出会いだったのですね。


- 松谷化学工業
- そうなんです。詳しく話を聞いてみると大学さんは、量産化した希少糖を、どう活用していいかがわからない、ということでした。当社は加工でん粉や難消化性デキストリンで、用途開発に取り組んだノウハウがあります。そこで大学・県と当社で共同し、製品化を進めよう、という話になりました。
- 取材担当者
- 取り組みが始まって、最も苦労したのはどんなところですか。
- 松谷化学工業
- 希少糖を厚労省に「食品」として認めていただくことです。これまでになかった製品ですから、定義からはじめなければなりません。厚労省の区分では「食品」と「食品添加物」のいずれかにカテゴライズされるのですが、当社としては希少糖は「食品」であると考えておりました。そこで当社、香川県、香川大学が協力し、様々な資料を集めて説明することで、食品だと認めていただくことができました。
- 取材担当者
- そして 2011 年、希少糖含有シロップ「レアシュガースウィート」発売にいたるわけですね。
- 松谷化学工業
- レアシュガースウィートは異性化糖を原料に、さらに異性化して製造されたもので、ブドウ糖、果糖を主成分に、希少糖を 15% 程度含んでいます。甘みは砂糖の 90% 程度で、含有している希少糖「アルロース」には、食後の血糖上昇抑制作用、内臓脂肪蓄積抑制作用やアンチエイジング効果が認められています。 ご家庭では砂糖よりヘルシーな代替品として、また企業様には機能性素材として活用していただけます。
- 取材担当者
- 数年前、テレビ番組に取り上げられて大ブレークしたそうですが。
- 松谷化学工業
- 問い合わせが殺到し、一時は生産が間に合わないほどでした。来年は単体の希少糖も製品化し、上市予定です。
- 取材担当者
- 希少糖ではどのような知財を取得しているのですか。
- 松谷化学工業
- 希少糖自体は自然界にあるものなので、知財化は難しいのです。そこで主に製造方法を香川大学さんと共同で特許化しています。

知的財産教育で研究員の意識を高める
- 取材担当者
- 難消化性デキストリンのお話で感心したのは、御社は開発初期に特許で製品や製法をしっかり守り、その間にデータやノウハウを蓄積することで、特許が切れても他社が参入できないような顧客の囲い込みが出来上がっているという点です。知的財産全般を非常にうまく運用されていますよね。
- 松谷化学工業
- ありがとうございます。

- 取材担当者
- 知的財産については専門部署を設けているのでしょうか。
- 松谷化学工業
- はい、研究所の中に知財グループを置いています。メンバーは 3 人です。
- 取材担当者
- 思ったより少人数なんですね。

- 松谷化学工業
- 研究員が知的財産の知識を持っていれば、3 人でも十分です。意識の高い研究員は、開発の早い段階で「この発明はこういう用途として知財化できるのでは」というふうに、私たちに話を持ってきてくれます。
- 取材担当者
- なるほど。そのような関係性ができていれば、知的財産担当者がヒアリングする手間が省けますね。研究員の方の知的財産への意識を高めるために実施していることがあれば教えていただけますか。
- 松谷化学工業
- 知的財産教育には力を入れています。外部の機関に委託したセミナーを実施するほか、我々知財グループで、若手研究員主体の勉強会を開くこともあります。
- 取材担当者
- 教育の対象者は研究員の方だけですか。
- 松谷化学工業
- 今のところはそうですね。本当は営業の方にも知的財産の知識を持ってもらえたら、とは思いますが、そこまで手が回らないのが実情です。ただ、営業マンには、もし得意先で「特許」という言葉を聞いたら、必ず研究所か知財にフィードバックするように、とお願いはしています。
- 取材担当者
- 教育以外に力を入れていることがあれば教えていただけますか。
- 松谷化学工業
- 調査活動には力を入れています。同業他社の動向について、国内だけでなく海外も対象にして定期的に調査しています。もちろん出願の際も、新規性があるかどうか先行技術調査を徹底して行います。
- 取材担当者
- 海外での出願では苦労も多いのではないですか。


- 松谷化学工業
- そうなんです。当社が出願作業をお願いしている外部の弁理士さんに特に求めているのは海外出願の知識やノウハウです。私は弁理士資格を持っていますので、国内の事についてはほぼ分かります。ただ、海外の知的財産までは正直追いきれていません。当社のパートナーとなる弁理士さんには、各国の法規制や現地の事情を、もっと教えて頂ければと思いますね。
- 取材担当者
- なるほど。日本弁理士会の会員には、各国の法規制や現地の事情に通じた方も多くおられますので、ぜひ弁理士を有効に活用して頂き、御社のクローバルな事業活動や知財活動にお役立てください。本日は貴重なお話をありがとうございました。

松谷化学工業株式会社
1919 年、創立者、故松谷亀一郎が大阪市鎗屋町で創業。以来、食品業界に「安心・安全・安定供給」を追求した多種多様な加工でん粉製品を提供し、高い評価を得ています。また近年はでん粉から開発した「難消化性デキストリン」や「希少糖含有シロップ」などの機能性素材も製品化。世の中のニーズに応える素材メーカーとして成長を続けています。
2019年6月4日掲載




