商標登録第5028951号
商標登録第6402255号
日本のタオル発祥の地、泉州で生まれた泉州タオルのブランド戦略とは

日本のタオル生産発祥の地が、大阪府泉佐野市ということをご存じでしょうか。日本初のタオル織機が開発され、生まれたのが「泉州タオル」です。そんな泉州にタオル製造のノウハウを学びに各地から技術者が訪れました。高い吸水性を誇る泉州タオルの歴史や、その発展に知的財産がどのように関係したのかを伺いました。
日本のタオル発祥は泉州 国産タオルが生まれた歴史を探る


- 取材担当者
- 日本におけるタオルの歴史は、大阪の泉佐野から始まったと聞きました。
- 大阪タオル工業組合
- 大阪府南部にある泉州地域は、江戸時代の頃から温暖で雨の少ない瀬戸内海式気候を利用して綿作りが盛んでした。その綿を紡績技術で糸に加工し、手ぬぐいやさらし木綿といった綿布の製造、販売で商売をする人が多かったのです。
- 取材担当者
- もともと綿を使った織物が盛んな地域だったのですね。
- 大阪タオル工業組合
- そうです。やがて1887(明治20)年に、佐野村(現在の泉佐野市)で白木綿業を営んでいた里井圓次郎氏が、タオル生地を織る機械を開発しました。表面を平らに織り上げる手ぬぐいに対し、タオルは表面の糸がループ状になっています。それがふわふわした肌触りの理由です。里井氏はそんなドイツ製のタオルを見て研究し、綿布を織る機械を、自らの手でループを作れる織機に改良、開発しました。翌年、中井茂右衛門氏がそれを「打出機」と名付けました。
- 取材担当者
- 海外から機械を輸入するのではなく、里井氏は自らの手で開発したのですね。だから、里井氏は日本のタオル創始者と呼ばれているのですね。「打出機」は、特許を取得していたのでしょうか?
- 大阪タオル工業組合
- 残念ながら、特許について明記された資料は残っていません。ただ、里井氏が打出機を開発してから7年後の1894(明治27)年に他の地域でもタオル製造が始まり、打出機もそこにあったようです。ということは恐らく、特許を取っていなかった可能性が高いと思われます。

- 取材担当者
- 日本の特許制度は、専売特許条例が施行された1885(明治18)年7月に始まりましたから、まだ特許への意識がなかったかもしれません。
- 大阪タオル工業組合
- そうです。タオルの製造技術は、愛媛県の今治市のほかに三重県の津市、あと福岡県の久留米市や東京都の青梅市にも広がりました。泉州と併せて一時、タオルの5大産地とも言われましたが、現在はここ大阪の「泉州タオル」、愛媛の「今治タオル」で日本の2大産地と言われており泉州と今治とで、国産タオルの97~98%を生産しています。
産地エリアで分業制を敷くタオル製造の仕組み

- 取材担当者
- 泉州では、どのようにしてタオル産業が発展していったのですか?
- 大阪タオル工業組合
- 以前から綿づくりをしていた人たちが中心になって、「これからはタオルの時代だ」と畑や田んぼだった土地に工場を建て、織機を導入して生産を始めました。1906(明治39)年に、佐野村のタオル製造業者25名によって「佐野タオル共同会」が組織されます。やがて大阪一円に拡大し、1932(昭和7)年に設立されたのが「大阪タオル工業組合」です。
- 取材担当者
- ずいぶんタオル製造者が増えたのですね。
- 大阪タオル工業組合
- しかし業者が増え過ぎて企業整理や生産調整が行われたり、戦争で原材料となる綿が減少したりして、1952(昭和27)年に「大阪タオル調整組合」が設立されます。これが今の組合の前身です。それが1958(昭和33)年に中小企業団体法に基づき、「大阪タオル工業組合」に改称されました。
- 取材担当者
- ちなみに今、日本で綿は作られているのでしょうか?
- 大阪タオル工業組合
- 現在、工業用の綿はごく一部国内生産はございますがほぼ100%が海外で生産されています。紡績会社が輸入し、その中でタオル用の糸に加工したものをタオル関連業者が仕入れます。

- 取材担当者
- タオルの製造方法を教えてください。
- 大阪タオル工業組合
- タオル生産は、大きく3つの工程の分業制で行っています。まず1つ目がサイジング。これは紡績会社から「生糸(なまいと)」と呼ばれる生成り色の糸を固く巻いた「綿糸」を購入し、糸巻機にかけます。その後強度を増すため、また織るときに滑りが均等になるようのりを付け、乾かして再度巻き直します。

- 取材担当者
- サイジングは、タオル織機にかける前の下準備というわけですね。
- 大阪タオル工業組合
- そうです。2つ目の工程が、タオルを織る作業です。一般的にタオルメーカーと呼ばれているのが、この織機でタオルを織る工程を担う会社ですね。ここで織り上げた布は、生成り色。まだ着色されていません。しかも裁断もしていないので、長い布です。
- 取材担当者
- タオルメーカーでは織るだけなのですね。
- 大阪タオル工業組合
- それをタオルに加工していくのが3つ目の工程で、「後ざらし」という作業を行います。植物由来の油分や不純物、また織る前に付けたのりを徹底的に洗い漂白します。やがて白くなった布を、ピンクや青に染めたりプリントしたりした後、裁断の作業を行います。泉州タオルは織り上げた後にさらしを行う後ざらし製法のタオルです。


- 取材担当者
- 工程ごとに、それぞれ担当する企業が違うのですか。
- 大阪タオル工業組合
- そうです。1社で3つの工程全てを行おうとすると、大規模な設備投資が必要になります。タオルの産地と呼ばれる地域は、こうした各工程の作業を行う中小企業が多く集まっています。これは泉州タオル以外の産地も同じです。泉州地域では、サイジングは3~4社。タオルメーカーは約70社。後ざらしを行う会社は約4社あります。タオルメーカーは織機でタオルを織るだけなので、中には従業員が社長1人というメーカーもあります。1工程目のサイジングと、3工程目の後ざらしは、導入する機械の規模が大きく、従業員数も10名~100名ほどおられますね。
- 取材担当者
- 先ほど「泉州タオルは後ざらしタオル」と仰いましたが、後ざらしは珍しいのですか?
- 大阪タオル工業組合
- いえ。「後ざらし」は日本だけでなく、世界のスタンダードです。なぜなら後ざらしを行うことで、吸水性がぐっと高まるからです。製法としては、「後ざらし」以外に「先ざらし」があります。
- 取材担当者
- 先ざらしと後ざらし、夫々の特長をお教え頂けますでしょうか?
- 大阪タオル工業組合
- 先ざらしのタオルは柄織(がらおり)ができて見た目が華やかなのが特長で、贈答用に向いています。ただサイジングの段階でのりを付けて織った後、十分にのりを落とせないため吸水性が悪かったのですが、近年では吸水性を高めるための改善が進みました。それに対して後ざらしの泉州タオルは吸水性が抜群なのが特長で、日常使いに向いています。ただ、柄織ができないので色も単色が多く、見た目の華やかさに欠けます。このため、泉州タオルも色柄を足すための研究を重ねています。
商標登録でブランドを守り強化してきた
- 取材担当者
- 泉州タオルとしてブランド化する方向へ舵を切るきっかけはあったのですか?
- 大阪タオル工業組合
- 2005(平成17)年に、「泉州こだわりタオル」を商標登録しました。さらに組合企業10数社が、それぞれ高付加価値を付けたギフト用タオルを作り、売り出していこうと独自のこだわりタオルを出展しました。それが「泉州こだわりタオル展」です。大阪と東京で年2回、2年間にわたり開催しました。さらに2007(平成19)年に「泉州タオル」で地域団体商標を取れたことで、ブランド化への機運が高まりました。
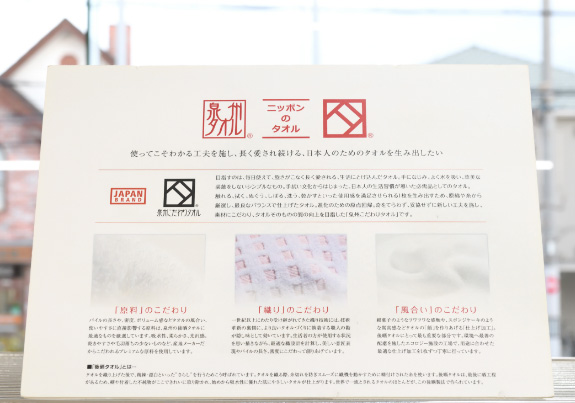
- 取材担当者
- 経済産業省による地域団体商標制度は、2006年4月に導入されましたから、その直後に申請、取得されたのですね、組合の中で、ブランド化への足並みがそろっていたように思われます。
- 大阪タオル工業組合
- そうです。文字について地域団体商標を取りましたし、泉州タオルのロゴマークについても商標登録を取りました。それまで各社独自のロゴマークでタオルを製造販売していたのが、組合員が泉州タオルのロゴマークを自社商品のタグなどに使用することで、皆で協力して泉州タオルをPRしようと盛り上がりました。ロゴマークが、まさに統一のシンボルマーク的な役割を果たしたと思います。
- 取材担当者
- それによって、組合に入る業者もあったのでは?
- 大阪タオル工業組合
- 実際に取引先様から、「泉州タオルのロゴマークを付けてほしい」と依頼されたという理由で、組合に入っていただいた会社が数社ありました。それまで組合の事業者は減少の一途でしたが、ブランド化したおかげで組合に入ろうという動きが生まれました。現在の組合員は69社あります。
- 取材担当者
- 泉州タオルという統一のロゴマークがあると、同じ泉州タオルでも、マークがあるものとないものとだと、やはりマークのあるものを選んでしまいますね。ロゴマークのデザインは、どういった経緯で決まったのですか?
- 大阪タオル工業組合
- 「泉州こだわりタオル展」以前に、タオルシンフォニーという小規模の展示会を開いていました。その際のプロジェクトメンバーにいたチーフデザイナーの方に、ロゴマークを作っていただきました。できるだけわかりやすくと、「泉州タオル」の文字にデザイン性をもたせたものにしました。手をつないだ感じが良いでしょう?

- 取材担当者
- 商標登録しているロゴマークがかなりおありのようです。
- 大阪タオル工業組合
- 登録したものの、使う機会が減って終了したものも幾つかありますが、まだまだありますね。
- 取材担当者
- 「泉州こだわりタオル」と「泉州タオル」の違いは何ですか?
- 大阪タオル工業組合
- 「泉州こだわりタオル」は、「泉州タオル」よりさらにワンランク上の高付加価値のあるタオルで、ギフトにもふさわしいタオルです。そのため審査では、独自の基準を満たした高いレベルのものだけを認定しています。審査では外部の方も入れた認定委員会を開き、製造した企業にはタオルの特徴やその意図、そしてこだわりをヒアリングして認定の判断材料にしています。

- 取材担当者
- 「水とともに生きる 泉州タオル」とは何でしょうか?
- 大阪タオル工業組合
- 一言で言えばリブランディングの事業です。泉州タオルは、2020(令和2)年に近畿経済産業局から「近畿を代表する10ブランド」に認定され、産地のアクションプランを作成したのです。現状と課題、その打開策と5年、10年後の未来にどうなっていたいかというプランで、その具現化に向け立ち上げたのが「水とともに生きる 泉州タオル」です。
- 取材担当者
- なぜ、「水とともに」なのですか。
- 大阪タオル工業組合
- 泉州では約140年もの間、タオルが作られてきています。タオル製造では、「さらし」の工程で水を大量に使います。その水は、泉州山脈の地下水で軟水。軟水は、白いタオルづくりに非常に適した水で、実際「泉州タオルといえば白タオル」と言われてきました。泉州の「泉」は、白に水と書きます。まさに白タオルを支える水を表現したロゴマークに決定しました。

- 取材担当者
- そういわれて見ると、確かに「白」と「水」という漢字を意識したロゴマークに見えます。
- 大阪タオル工業組合
- ゆくゆくは、現在の泉州タオルのロゴマークから、この「水とともに生きる 泉州タオル」のロゴへ変更していきたいと考えています。そのために、泉州タオルの歴史やものづくり、作り手の顔、どんな商品を作っているのかといった、背景まで表現しブランド化して、国内外にPRしていきたいと思っています。普段の生活シーンで選ばれる、高品質タオルブランドであり続けたいと思います。
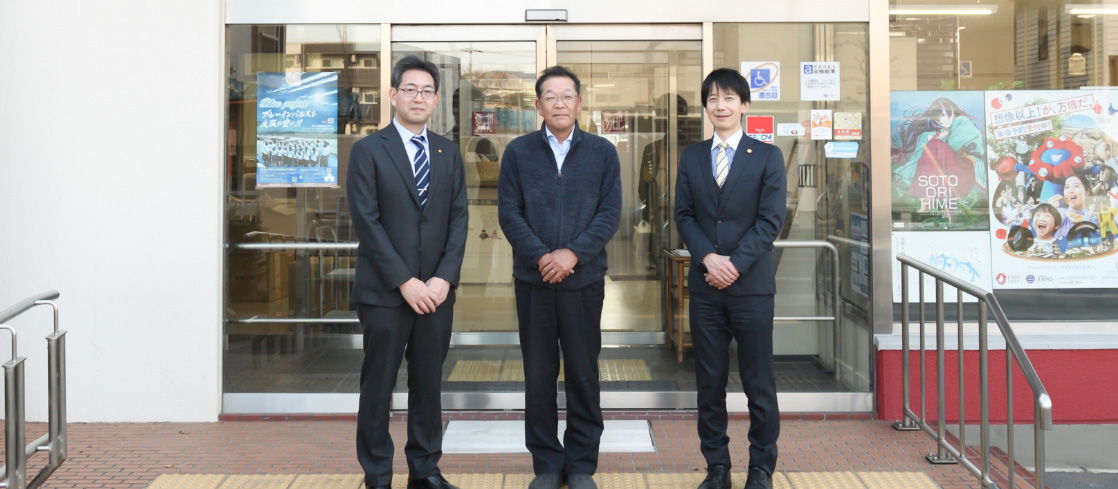
- 取材担当者
- 安心してPRするためにも、きちんと商標登録しておられるのですね。
- 大阪タオル工業組合
- 自分のところのブランドなのに、いざ商標登録しようと思ったら全く関係のないところに登録されていた、などという話もあります。やはりきちんと押さえておくことは大切だと考えます。
- 取材担当者
- 本日はお忙しい中をありがとうござました。

大阪タオル工業組合
1952(昭和27)年に、前身である「大阪タオル調整組合」が設立され、1958(昭和33)年に「大阪タオル工業組合」に改称し現在に至る。国内外に向けて泉州タオルの普及と認知向上に力を入れており、「タオル王国」や「泉州こだわりタオル」などの商標登録をはじめ、2007(平成19)年には地域ブランド「泉州タオル」を商標登録した。現在リブランディング事業である「水とともに生きる 泉州タオル」事業を推進。泉州タオルの歴史や取り組み、また製造者の思いなど産地全体をアピールすることでファンを獲得している。2025(令和7)年の大阪・関西万博でも展示予定。
2025年3月10日掲載




