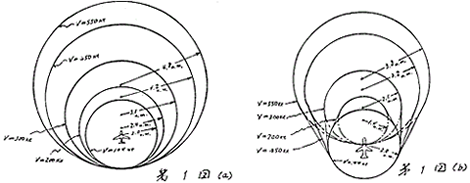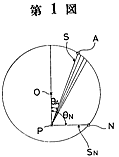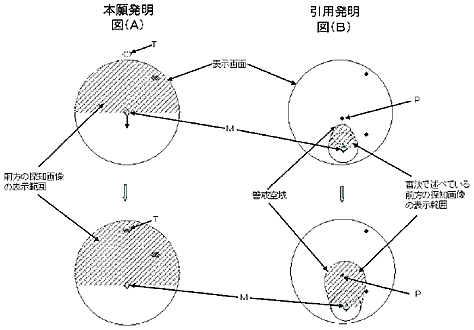平成20年12月25日判決 知的財産高等裁判所 平成20年(行ケ)第10130号
- 事件名
- :レーダ事件
- キーワード
- :進歩性,組み合わせ容易とした判断の誤り
- 関連条文
- :特許法29条2項
- 主文
- :特許庁が不服2006-426号事件について平成20年2月25日にした審決を取り消す。(以下,省略)
1.事案の概要
本件は,発明の名称を「レーダ」とする特許出願について拒絶査定を受けた原告が不服審判を請求したところ,特許庁は,本願発明は特開昭61-79179号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに特開昭59-17177号公報及び特開昭54-64991号公報に記載の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとして拒絶審決をしたので,原告がその審決の取り消しを求めた事案である。
原告主張の審決取消事由は,引用発明の認定の誤り,引用発明との一致点の認定の誤り等も含めて多岐に亘るが,判決では,「相違点2係る容易想到性判断の誤り」の点のみが判断された。
2.事件の経緯
平成 8年12月 3日 出願
平成17年 5月10日 拒絶理由通知書
平成17年 6月27日 意見書
平成17年 6月27日 手続補正書
平成17年12月 6日 拒絶査定
平成18年 1月 5日 審判請求
平成20年 2月25日 審決(請求不成立)
平成20年12月25日 判決(審決取消)
3.本願発明の内容
本願明細書(平成17年6月27日付手続補正後のもの)の特許請求の範囲および発明の詳細な説明の欄には,以下の記載がある(下記(ア)(ウ))。また,図1には,本願発明の実施形態に係るレーダの表示例が図示されている(下記(イ))。
|
(ア) |
特許請求の範囲(請求項2以下は省略) 【請求項1】 アンテナの指向方向を順次変えるとともに,パルス電波の送受波を行い,アンテナ周囲の探知画像のデータを生成し,所定の範囲の探知画像を表示画面内に表示する移動体に装備されるレーダにおいて, 前記移動体の移動速度を検知する移動体速度検知手段を備え, 表示画面内における移動体の表示位置を前記表示画面内の基準位置から移動体の移動方向に対して後方へ所定のシフト量だけシフトさせて前記探知画像を表示し,前記移動体速度検知手段により検知された移動体の移動速度が大きくなるほど,前記シフト量を大きくする探知画像表示制御手段を設けたことを特徴とするレーダ。 |
|
(イ) |
図面(図2以下は省略) 【図1】 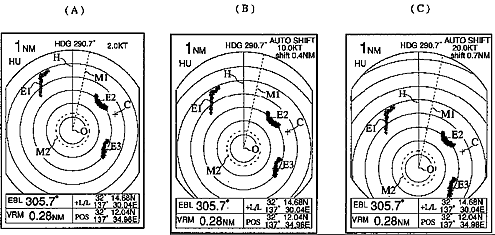 |
|
(ウ) |
発明の詳細な説明(抜粋) 【0001】【発明の属する技術分野】この発明は,船舶などの移動体に装備されるレーダに関する。 【0002】【従来の技術】船舶などで用いられる従来のレーダは,アンテナの指向方向を順次回転させるとともに,パルス状の電波を送受波し,アンテナの指向方向と受波タイミングに応じてアンテナ周囲の探知画像のデータを生成し,これを表示装置に表示することによって,自船周囲の物標を監視するものであるため,基本的に自船の位置を探知画像の中心として探知画像を表示するようにしている。そして,操作者は自船周囲の物標監視の目的に応じて表示レンジを切り換えるようにしている。また,船舶が航行しつつ前方の広い範囲に注意を払って物標の監視を行えるように,表示画面の下方寄りに自船位置を配置して,自船前方の表示範囲を広くとるようにするシフトまたはオフセンターと称される機能(以下「シフト機能」という。)を備えている。 【0003】【発明が解決しようとする課題】上記シフト機能によって,探知画像をどれだけシフトさせて表示させるか,そのシフト量は,表示レンジに応じて一義的に定めることができず,その時に設定されている表示レンジに応じて,また物標探知や物標監視の目的(移動速度が速い場合に,前方のより広範囲を監視する等の目的)に応じて設定することになるが,レーダの操作者が,実際に表示されている探知画像を確認してシフト量を判断しなければならず,その操作は煩雑であった。 【0004】勿論,表示レンジを大きくして探知範囲が広くなるように設定しておけば常に広範囲の探知が可能であるが,表示レンジが大きいほど物標が相対的に小さく映るので,物標の形を識別したい場合には不適当となる。そのため,常に大きな表示レンジで表示しておくことは現実的ではない。 【0005】この発明の目的は上記シフト量の設定をできるだけ操作者の手を煩わせることなく,最適なシフト量となるようにしたレーダを提供することにある。 【0006】【課題を解決するための手段】この発明は,アンテナの指向方向を順次変えるとともに,パルス電波の送受波を行い,アンテナ周囲の探知画像のデータを生成し,所定の範囲の探知画像を表示画面内に表示する移動体に装備されるレーダにおいて,上記シフト量設定の煩雑さを解消するために,請求項1に記載のとおり,前記移動体の移動速度を検知する移動体速度検知手段を備え,表示画面内における移動体の表示位置を,前記表示画面内の基準位置から移動体の移動方向に対して後方へ所定のシフト量だけシフトさせて前記探知画像を表示し,前記移動体速度検知手段により検知された移動体の移動速度が大きくなるほど,前記シフト量を大きくする探知画像表示制御手段を設ける。 【0029】【発明の効果】請求項1に記載の発明によれば,移動体の移動速度が大きくなるほど,表示画面内における移動体の表示位置が前記表示画面内の基準位置から移動体の移動方向に対して後方へシフトして探知画像が表示されるため,移動体の移動速度が低速な状態ではシフト量があまり大きくならずに,移動体の前方も後方も略等しい範囲を探知および監視でき,移動体の移動速度が大きくなると,後方より前方の表示範囲が広く取られて,前方のより広い範囲を監視できるようになり,操作者の手を煩わせることなく,移動速度に応じて常に最適なシフト量が確保される。 |
4.引用発明及び周知技術の内容
|
(ア) |
特開昭61-79179号公報(引用発明) 特許庁が主引例として挙げた上記引用刊行物には,第1図に,引用発明の実施形態に係る警戒空域表示方式の例が示されている(下記(a))。また,明細書の特許請求の範囲および発明の詳細な説明の欄には,以下の記載がある(下記(b))。
|
||||||||||
|
(イ) |
特開昭59-17177号公報(周知技術) 特許庁が周知技術(副引例)として挙げた上記刊行物の第1図には,従来のオフセンタによるPPI掃引を示した図面が示されている(下記(a))。また,明細書の発明の詳細な説明の欄には,以下の記載がある(下記(b))。
|
||||||||||
|
(ウ) |
特開昭54-64991号公報(周知技術) 特許庁が周知技術(副引例)として挙げた上記刊行物には,明細書の発明の詳細な説明の欄に,以下の記載がある。 「・・又特に船舶レーダ等において進路方向を主に表示するなどのため,走査線の起点即ち像の原点をCRTの画面の中心から外すこと即ちオフセンタとした場合は,カーソル板の中心と掃引の中心がずれるので方位を正確に測定できなかった。」(公報第1頁右下欄下から2行~2頁左上欄4行) |
5.審決の内容
審決は,「本件審判の請求は,成り立たない。」と結論した。審決が認定した引用発明の内容,本願発明と引用発明との一致点及び相違点,並びに相違点2に関する判断は,以下のとおりである。
|
(ア) |
引用発明の内容 「自航空機の衝突防止装置が発する質問信号に応答する他航空機のATCトランスポンダ応答信号を受信し,その受信電界強度,方位等から他航空機の概略位置を把握しこれをCRT上の警戒空域内に表示する航空機衝突防止装置において,対気速度計の指示する自航空機速度情報を計算機に入力し,これに基づいて,自航空機を中心とする所定半径の円と,前記円の中心を通り前記自航空機の速度に応じてその進行方向に直径が伸縮する円との外周を結ぶ如きプロファイルを有する警戒空域をCRT上に表示し,自航空機の速度が増大するに従って前記直径を伸張することを特徴とする航空機衝突防止装置。」 |
|
(イ) |
本願発明と引用発明との一致点 「電波の送受波を行い,周囲の探知画像のデータを生成し,所定の範囲の探知画像を表示画面内に表示する移動体に装備される電波を利用した航法装置において,前記移動体の移動速度を検知する移動体速度検知手段を備え,表示画面内における移動体の表示位置より移動体の移動方向からみて前方の探知画像の表示範囲を移動体の移動速度に応じて広げることを特徴とする電波を利用した航法装置。」 |
|
(ウ) |
本願発明と引用発明との相違点 [相違点1] 電波を利用した航法装置が,本願発明では,「アンテナの指向方向を順次変えるとともに,パルス電波の送受波を行い,アンテナ周囲の探知画像を表示するレーダ」であるのに対し,引用発明では,ATCトランスポンダを利用したものである点。 [相違点2] 探知画像の表示の変更に関して,本願発明が「表示画面内における移動体の表示位置を前記表示画面内の基準位置から移動体の移動方向に対して後方へ所定のシフト量だけシフトさせて前記探知画像を表示し,前記移動体速度検知手段により検知された移動体の移動速度が大きくなるほど,前記シフト量を大きくする探知画像表示制御手段を設けた」のに対し,引用発明はこのような構成を具備しない点。 |
|
(エ) |
相違点2に関する判断 「引用発明において,自航空機を中心とする所定半径の円と,前記円の中心を通り前記自航空機の速度に応じてその進行方向に直径が伸縮する円との外周を結ぶ如きプロファイルを有する警戒空域をCRT上に表示し,自航空機の速度が増大するに従って前記直径を伸張するようにした趣旨は,引用刊行物の上記摘記事項3及び4の記載からみて,衝突回避操作に必要とされる時間を確保するために,自航空機の速度が増大するに従って,自航空機の前方の警戒空域の表示範囲をより広げるためである。 一方,航法装置において,移動体の前方の監視区域の表示範囲を広げるために,移動体の表示位置を表示画面の中心位置から後方へずらせて表示させることは,例えば,特開昭59-17177号公報,特開昭54-64991号公報に示されるように本願出願前周知である。 そうすると,引用発明と該周知技術は,ともに,移動体の前方の監視区域の表示範囲を広げるものであるから,引用発明に該周知技術を適用して,自航空機の速度が増大するに従って,自航空機の表示位置を表示画面の中心位置からより後方へずらせるようにすることは当業者が容易に想到し得たことである。 そして,その際に,引用刊行物の第1図(b)に示されるように,自航空機の移動方向の警戒空域を最も広く表示するためには,自航空機の表示位置を移動方向に対して後方へずらせばよいことは明らかである。 したがって,引用発明に上記周知技術を適用して相違点2に係る構成とすることは当業者が容易になし得たことである。」(審決書5頁15行~35行) |
6.判決の内容
|
(ア) |
主文 特許庁が不服2006-426号事件について平成20年2月25日にした審決を取り消す。(以下,省略) |
||||||||||
|
(イ) |
理由 裁判所は,審決の相違点2に係る容易想到性の判断には,誤りがあると判断した。その理由は,以下のとおりである。
|
7.検討事項
|
(ア) |
検討事項1
|
|||||
|
(イ) |
検討事項2
|
(執筆者 山本 進 )